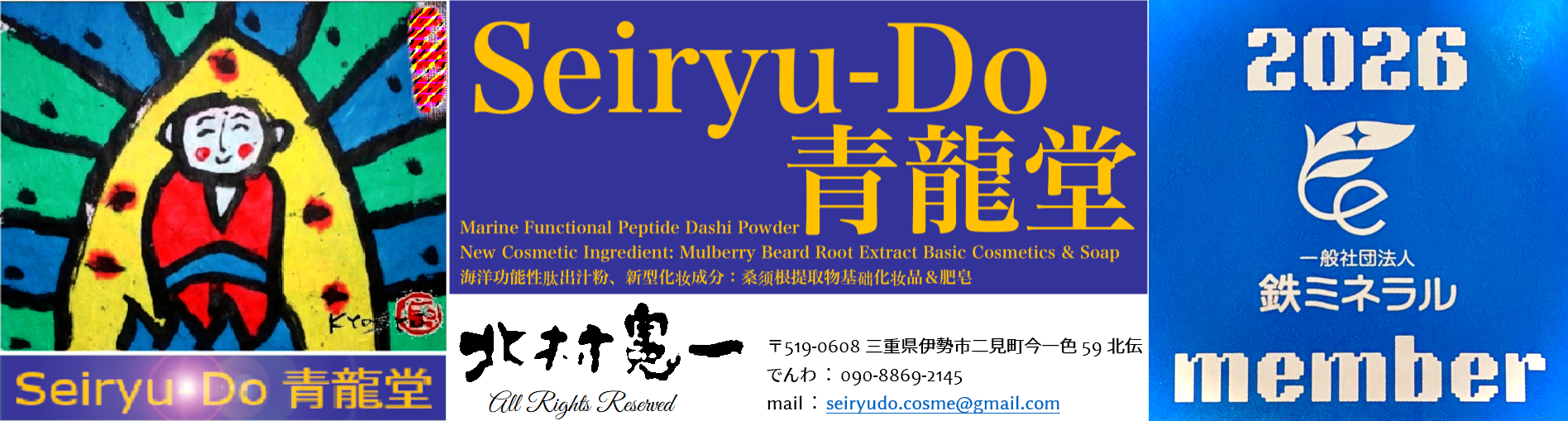2025/07/27 14:34
はじめに──母として、子の未来を支える身体の「設計図」を知っていますか?
私たちが日々目にする美容・健康・食に関する情報。その多くは「化粧品メーカー」「サプリ会社」「テレビ番組」「インフルエンサー」など、実は【誰が得をするか】を軸に作られた情報で溢れています。ですが、我が子の進学期という人生の大事な節目に、母として本当に大切にすべきは「見た目」ではなく、見た目の【奥】にある、体を作る本質です。
その中心にあるのが「コラーゲン」。
私たちの体の約30%を占めるこのたんぱく質は、美容だけでなく、学力や健康、骨格、脳機能にまで密接に関係しています。
しかし、その真の姿はあまりにも知られていません。
この文章では、コラーゲンの構造・機能・加齢変化・代謝の真実を、科学的根拠をもとに明らかにし、「正しい知識」で子どもと自分を守るヒントをお届けします。
もくじ:
【1】コラーゲンは【構造のすべて】に関与する
【2】なぜ【加齢】でコラーゲンは減少するのか
❶ 加齢による合成力の低下
※余談※
❷ 糖化(AGEs)と酸化による損傷
【3】コラーゲンの【代謝が遅い】という致命的な特性
【4】メーカーが教えてくれない【コラーゲン神話】の真偽
【5】【未来を支える体】をつくる母の選択
参考文献一覧

【1】コラーゲンは【構造のすべて】に関与する
コラーゲンは単なる「肌のハリ成分」ではありません。全身のあらゆる場所に存在し、人体の土台とも言える構造体です。
主要な存在部位(代表的な型と機能)
皮膚(Ⅰ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅶ型):
皮膚の真皮は約70%をコラーゲンが占め、体全体ではコラーゲンの約40%が皮膚に存在。肌の弾力と防御力の源。
骨(I型):
骨の90%以上はコラーゲンから構成。コラーゲン繊維は骨折予防の要であり、骨のしなやかさと強度を保つ働きがあります。
軟骨(Ⅱ型):
軟骨の弾力性と耐久性を保つ上で不可欠。損傷しやすく修復しづらい領域。
腱・靭帯(I型):
筋肉から骨への力の伝達路。ケガの予防・体の連動に関与。
血管(I, Ⅲ, V型):
血管の弾力性、特に高血圧や動脈硬化の予防に深く関与。
内臓(I, Ⅲ型):
肝臓・腎臓などの被膜と間質の支持構造。形態維持と機能支援に不可欠。
歯・歯茎(I型):
象牙質、セメント質、歯茎(歯肉)を形づくる。口腔の健康に直結。
眼(Ⅱ, V型):
角膜や硝子体を形作り、視覚の保持に寄与。
筋膜(I型):
筋肉全体を包む膜で、姿勢・柔軟性・運動効率の基盤。
毛乳頭(Ⅳ, ⅩⅦ型)・爪床(Ⅶ型)・これらを支える真皮(Ⅰ, Ⅲ, Ⅳ, Ⅴ, Ⅶ型):
髪の毛や爪を健康的に形成するための土台としての役割。
●参考文献:Prockop DJ et al., What holds us together? Why collagen is so critical, N Engl J Med. 1995
以下、主要な存在部位それぞれの詳細を見ていきましょう
皮膚 (真皮):
コラーゲンが最も多く存在する部位であり、体内の全コラーゲンの約40%が皮膚に存在します。特に、皮膚の真皮はコラーゲンが主成分であり、その70%を占めます。
皮膚のハリや弾力を保ち、シワやたるみを防ぐ上で重要な役割を果たします。主にI型コラーゲンとⅢ型コラーゲンが多く見られます。
骨:
骨はカルシウムやリンといったミネラルでできていると思われがちですが、その土台となる有機質の約90%以上がコラーゲン(主にI型)で構成されています。
コラーゲン繊維が骨のしなやかさと強度を保ち、骨折のしにくさに寄与しています。
軟骨:
関節の動きを滑らかにし、衝撃を吸収するクッション材の役割を果たす軟骨も、主要な成分がコラーゲン(主にⅡ型)です。
軟骨の弾力性と耐久性を保つ上で不可欠です。
腱(けん):
筋肉と骨をつなぐ腱は、非常に強い線維性の結合組織で、その主成分はコラーゲン(主にI型)です。
筋肉の力を骨に伝え、体の動きを可能にします。
靭帯(じんたい):
骨と骨をつなぎ、関節を安定させる靭帯も、コラーゲン(主にI型)でできています。
関節の安定性や可動域を制限する役割があります。
血管:
血管壁はコラーゲン(主にI型、Ⅲ型、V型)によって構成されており、血管の弾力性や柔軟性を保ち、血圧の変化に対応する上で重要です。
血管の健康維持にも深く関わっています。
歯(象牙質、セメント質など):
歯の硬い組織である象牙質や歯根を覆うセメント質なども、コラーゲンを多く含んでいます。
眼(角膜、硝子体など):
眼の透明性や形状を保つ角膜や、眼球の内部を満たす硝子体にもコラーゲン(主にⅡ型、V型)が含まれています。特に硝子体は、その大部分が水ですが、形状を保つためにコラーゲン(主にⅡ型)とヒアルロン酸が網目状に存在しています。
透明性とゲル状の特性は、眼の形状を維持し、光が網膜に届くまでの通路を確保するために不可欠です。
内臓の被膜・間質:
肝臓、腎臓、脾臓などの内臓は、それぞれを包む被膜や、臓器内部の細胞の間を埋める「間質」と呼ばれる結合組織にコラーゲン(主にI型、Ⅲ型)が豊富に含まれています。
これらのコラーゲンは、臓器の形態を保持し、細胞や血管、神経を支持する足場(スカフォールド)としての役割を果たしています。
髪の毛・爪(成長と構造の維持):
髪の毛や爪の主成分はケラチンというタンパク質ですが、その根元にある・毛乳頭や・爪床といった部分、そしてそれらを支える・皮膚組織にはコラーゲンが存在します。
コラーゲンは、これらの組織の成長に必要な栄養素を供給する血管を支えたり、髪の毛や爪が健康的に形成されるための土台としての役割を担っています。間接的ではありますが、その構造と成長に寄与しています。
・毛乳頭のコラーゲン:
毛乳頭は毛包の重要な部分であり、コラーゲン(主にⅣ型)が発毛の促進や維持に不可欠な細胞外マトリックスに埋め込まれています。
また、近年、ⅩⅦ型コラーゲンが髪や毛根部分に関与する可能性が指摘されており、毛包幹細胞の保護や抜け毛、髪の老化を遅らせるメカニズムに寄与すると考えられています。
・爪床のコラーゲン:
爪床は爪を支える組織で、コラーゲン(主にⅦ型)が爪の形状に関与することが示唆されており、その変異が爪の変形に関わる可能性が研究されています。
・皮膚組織(特に真皮)のコラーゲン:
皮膚の大部分を占める真皮は、主に下記のコラーゲンで構成されており、皮膚のハリや弾力を保つ重要な役割を担っています。
- I型コラーゲン: 皮膚に最も豊富に存在するコラーゲンで、皮膚のコラーゲンの90%を占めます。皮膚の強度や弾力性に関わります。
- Ⅲ型コラーゲン: I型コラーゲンと共存して真皮に多く含まれ、組織の柔軟性に寄与します。創傷治癒過程で一時的に増加し、I型コラーゲンに置き換わっていくことも知られています。
- Ⅳ型コラーゲン: 表皮と真皮をつなぐ基底膜に存在し、基底膜の骨格を形成します。
- V型コラーゲン: 真皮の再生に必須の真皮幹細胞の維持に重要な役割を果たすことが示唆されています。
- Ⅶ型コラーゲン: 基底膜と真皮をつなぎとめる役割を持っています。
筋肉の筋膜(ファシア):
筋肉そのものは筋繊維というタンパク質でできていますが、個々の筋繊維や筋束、そして筋肉全体を包み込む「筋膜(ファシア)」は、主要な成分がコラーゲン(主にI型)です。
筋膜は、筋肉の動きを滑らかにし、力を効率的に伝達するとともに、筋肉の形状を維持し、他の組織との摩擦を防ぐ役割を果たしています。この筋膜の柔軟性が失われると、体の動きが制限されたり、痛みの原因になったりします。
歯茎 (歯肉):
歯茎(歯肉)は、歯を支える土台となる非常に重要な組織です。この歯茎の主要な構成成分の一つがコラーゲン(主にI型)です。コラーゲン繊維が豊富に存在することで、歯茎は丈夫で弾力性を持ち、歯をしっかりと固定し、細菌の侵入から保護するバリアとしての役割を果たしています。健康な歯茎はピンク色で引き締まっており、この状態を保つには、コラーゲンの健全な状態が不可欠です。
このように、コラーゲンは私たちの体のあらゆる部位に存在し、それぞれ異なる構造と機能を持つ「型」が存在します。これらのコラーゲンが、体の形を維持し、組織に強度と弾力を与え、スムーズな身体機能を実現する上で不可欠な役割を担っています。
【2】なぜ【加齢】でコラーゲンは減少するのか
肌や関節の衰えが【見た目】に出てきた時、それは氷山の一角。
実は、見えない部分──骨や血管、内臓でも同様にコラーゲンは減少・劣化しています。
その主な要因が以下です:
❶ 加齢による合成力の低下
25歳をピークに、年々コラーゲンの合成力は低下します。
* 女性は閉経後、エストロゲンの減少とともに急激に減少
* 紫外線(主にUVA)、睡眠不足、慢性ストレス、糖質過剰摂取が合成阻害要因
※余談※
世間では、
① UVAの蓄積的ダメージ(長時間・日常):短時間でも毎日10〜20分の顔・腕などの曝露が数年単位で蓄積すると、真皮の構造に変化。窓ガラス越しでもUVAは防げない(UVBは遮断されるが、UVAは透過)。
② UVBの急性ダメージ(強光・レジャー):真夏の海辺などで30分〜1時間無防備で日光を浴びれば、表皮の炎症→真皮への炎症性サイトカイン波及が起こり、短期間でもコラーゲンにダメージを与える可能性あり。
とされ、日光にあたることが健康や美容を損なう原因であるという情報が溢れています。
しかし、
感染症対策に必要なビタミンD3(コレカルシフェロール)を体につくらせるには、
天高く登った(午前10時〜午後3時が推奨)太陽光線のUVB(波長280〜315nm)を、
本州では夏場に、顔+手+半袖(約15%露出状態)で15〜30分、半袖・膝丈(約30〜40%露出状態)で約10〜15分、それぞれ浴びること(UVBは窓ガラスで完全に遮断されるため、直接浴びる必要あり)によって、7-デヒドロコレステロールという前駆体からビタミンD3が合成されます。
しかし、12〜2月の冬場はほぼ不可能です。
北海道では10〜3月は事実上不可能です。
UVBを浴びるということは、思いの外、大変貴重なことなのです。
日光浴によるビタミンD3合成ができない期間は、食品によるビタミンD3(サケ、サンマ、イワシ、カツオなどの脂の乗った魚)、D2(紫外線に当ててあるキノコ類)摂取を心がけましょう。
また、
ビタミンD3と鉄は相互に影響し合う関係性があります。
ビタミンD3は鉄の吸収・代謝を助け(ヘプシジンを抑制し、鉄の小腸吸収・利用効率UP)、
鉄は活性型ビタミンD3の生成に不可欠です(活性化に必要な酵素(25-水酸化酵素(CYP2R1)や1α-水酸化酵素(CYP27B1))が鉄依存性)。Zughaier SM et al. The role of vitamin D in regulating hepcidin in anemia of inflammation. Nutrients. 2014.
これらの酵素は鉄を補因子(補酵素)として必要とする「鉄含有モノオキシゲナーゼ群(P450酵素群)」に属します。
よって、鉄欠乏ではビタミンD₃の活性化が不十分になる可能性があるのです。
Bacchetta J et al., Iron and vitamin D deficiencies in children with early chronic kidney disease. Pediatr Nephrol. 2014.
生活実践のヒント
「☀️日光+🐟魚+🍃桑甘露+🐟フィッシュボーンブロス舞茸プラス🍄🟫」=ビタミンD₃と鉄の『自家製造環境』を整える。
体内の合成力を高めることで、紫外線恐怖症ではない積極的な美容・健康維持が可能になります。
※余談終わり※
❷ 糖化(AGEs)と酸化による損傷
糖化とは、コラーゲンが余分な糖と結びつくことで「焦げついたような」硬い構造に変性する現象です。
この変性したコラーゲンは機能を失い、体内で分解・再生がほとんど行われないため、劣化したまま体内に残ります。
* コラーゲンの糖化と酸化は、肌のたるみ、骨粗しょう症、関節炎、動脈硬化など全身病態の原因
* 特に骨の糖化は【折れやすい骨】をつくる最大要因(参考:Saito M, Marumo K. Collagen cross-links as a determinant of bone quality, Bone. 2010)
【3】コラーゲンの【代謝が遅い】という致命的な特性
一般的なたんぱく質は、1日~数週間で新陳代謝しますが、コラーゲンはそうではありません。
皮膚のコラーゲン:半減期 約15年
軟骨のコラーゲン:半減期 約117年(Human cartilage)
つまり、劣化したコラーゲンは完全に元の状態に戻ることは困難です。
すなわち「入れ替わる」のではなく、「そのまま残ってしまいがち」なのです。
このため【予防】がすべてのカギ。
例えば:
* ミネラルと酵素が抜けた高糖質のおやつ・ジュースを控える
* 睡眠ホルモン(メラトニン)の分泌を促す夜間の照明管理 → そのためにはフィッシュボーンブロス舞茸プラスを多めに摂取❣️
* 抗酸化食材(桑甘露、ビタミンC、アントシアニン)の活用
桑甘露の力強い抗酸化力が、真夏のUVの悪影響からあなたを守ってくれます。
桑甘露の特徴(論文からの要点)
● 桑甘露は、通常の桑葉よりもポリフェノール含有量が顕著に高く(特に抗糖化性)、タンパク質や脂質の変性を抑える作用を持つことが確認されています(【BMS-CNT-2023-11】)
→ 加齢とともに酸化・糖化が蓄積するコラーゲンの質を守るという観点で重要。
● ヒト線維芽細胞に対し、桑甘露抽出物は鉄排出を抑制し、GLO-I(グリオキサラーゼⅠ)の活性を維持する働きが確認されています。
→ 鉄不足による糖化促進(AGEs蓄積)を未然に防ぐ効果に寄与。
● 一般的な桑葉との最大の違いは、水耕栽培による農薬フリー+葉齢と葉面積を制御し、さらに低温で乾燥している点。これにより:
・ビタミンC含有が高く維持されている
・鉄・シリカの植物内濃度が上昇
・デオキシノジリマイシン(DNJ)やカフェオイルキナ酸などの生理活性成分が高濃度化
吸収利用されやすいコラーゲン・ペプチドや、カツオ、カタクチイワシを頭から尻尾の先まで丸ごと使用しているため、コラーゲン以外の海洋ペプチドも鉄分や亜鉛も豊富に含みます。また、睡眠の質を高めるメラトニンの素となる幸せホルモン「セロトニン」を体につくらせる原料を多く含んでいます。また、シリカ(ケイ素)にも富んでいます。
【4】メーカーが教えてくれない【コラーゲン神話】の真偽
✖「コラーゲンを食べればそのまま肌に届く」は幻想
食事で摂取されたコラーゲンは、消化酵素によってペプチドやアミノ酸に分解されます。
分解後、体内で再び【どのたんぱく質になるか】は体が決定します。
特定のペプチド(例:Pro(プロリン)-Hyp(ヒドロキシプロリン)、Pro-Hyp-Gly(グリシン)、等)には【コラーゲン合成促進】作用があるとする研究もあります(Iwai K. et al., J Agric Food Chem. 2005)。
この研究は、経口摂取されたコラーゲンが消化管で分解され、一部がペプチドの形で吸収され、血中に移行することを示しています。
これは、コラーゲンが単にアミノ酸として吸収されるだけでなく、生理活性を持つ可能性のある特定のペプチドとして吸収されることを示唆する重要な知見です。
◎正しくは「体内の合成環境を整える」ことが第一
* ビタミンC:コラーゲン合成に不可欠
* 鉄:ヒドロキシル化反応の補酵素として必要(ProをHypに変える反応)
* シリカ、亜鉛、アミノ酸(グリシン(Gly)・プロリン(Pro))も補因子として必須
● 正しい食品例とは?:
次回のブログではこれについて、ビタミンC、鉄、シリカ、亜鉛、グリシン、プロリンに分けて推奨食材をあげていきます。皆さんなら、もう、お分かりですね❣️
【5】【未来を支える体】をつくる母の選択
進学を控える子どもたちは、身体的にも精神的にも最も成長する時期にいます。
その骨格、脳、免疫、集中力を支える土台──それがコラーゲンを中心とした「構造の健全性」です。
あなたの1日3食、何を食べ、どんな生活リズムを与えているかが、子どもの未来を支えます。
SNSやマスコミの【きれいごと】に惑わされず、科学的根拠や由緒ある伝統に基づいた情報で行動する勇気を。
それが、未来を支える本物の「教育」です。
参考文献一覧
1. Saito M, Marumo K. Collagen cross-links as a determinant of bone quality. Bone. 2010.
2. Iwai K, et al. Identification of food-derived collagen peptides in human blood after oral ingestion of gelatin hydrolysates. J Agric Food Chem. 2005.
3. Prockop DJ, Kivirikko KI. Collagens: molecular biology, diseases, and potentials for therapy. Annu Rev Biochem. 1995.
4. Bailey AJ. The collagen family and the diseases associated with abnormalities of collagen metabolism. Br Med Bull. 1985.
5. S. Buehler MJ. Nature designs tough collagen: Explaining the nanostructure of collagen fibrils. Proc Natl Acad Sci USA. 2006.